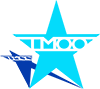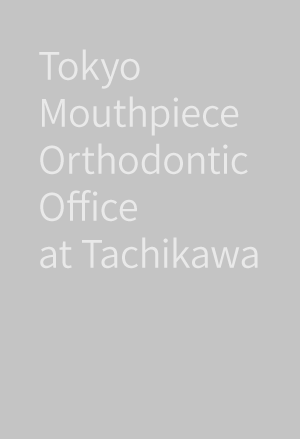対象年齢
上下の顎骨の成長がおよそ終了したと判断できる場合は治療可能です。歯列矯正は、歯と骨の間にある歯根膜という組織に弱い炎症性反応を起こし、生体反応を利用することで歯の移動を可能にします。そのため歯周組織の状態が正常であれば、特に年齢に制限などはなく治療が可能です。ただし、生体反応であるため、個人差が大きく、一般的に若年齢の方が、骨代謝が良いため動きが良いと言われています。
治療の必要性
歯は口腔周囲の筋肉のバランスが保たれたところに並ぶため、矯正前の歯並びは一つの安定した位置であるとも考えられます。そのため、清掃性、機能性などに問題がなければ特に治療の必要はないと思います。
しかし、口元の突出感や隙間、叢生などは矯正治療で審美的な部分は大きく改善されます。そのため、患者の主訴や希望によっては矯正治療を行う必要があります。
治療期間は?
治療期間に関しては、歯並びによっても大きく異なるため個人差が大きいです。大きな隙間を閉じたり、移動量が多いものに関しては時間がかかります。
一般的な抜歯部位として選択されることの多い小臼歯抜歯による治療は2年半ほどかかることが多いです。
歯の移動は生体反応を利用しているため、移動速度を変えることはできませんが、矯正用アンカースクリューなどによって多くの歯を一度に動かす場合には期間の短縮が可能な場合があります。
治療のゴールは?
機能的に問題がないことを前提として、審美的であることが求められます。ただし、ゴールについては人それぞれであるため、事前にシミュレーションなどを通して患者のゴールと矯正医の考えるゴールをすり合わせておくことが重要です。また、それに加えて、何に比重を置くかも考えなければなりません。歯を絶対に抜きたくないなどの希望は事前に伝え、その場合の治療ゴールを明確にしておく必要があります。
リスク・デメリット
歯根吸収
歯の移動は、弱い炎症を引き起こし、骨を改造する細胞を誘導することで可能になります。骨を改造する細胞(もしくは類似細胞)は歯根を吸収してしまうことがあります。
また、移動によって硬い皮質骨に接触すると構造的に吸収してしまうこともあります。
歯肉退縮
歯の移動は骨改造により可能になりますが、その過程での骨吸収によって骨が減少してしまうことがあります。骨は歯茎に覆われているため、その上の歯茎が下がって見えることがあります。これを歯肉退縮と言います。骨質を個人差があり、もともと骨が薄いタイプは歯肉退縮を起こしやすいです。
歯髄壊死
歯髄とは、歯の中の神経や血管などが入っている空洞のことであり、歯自体の恒常性の維持に重要です。歯の移動によって歯髄への血流が遮断され、歯髄が壊死してしまうことがあります。これによって、歯が黒く見えたり歯自体の感覚が鈍くなったりします。
歯牙強直(アンキローシス)
歯と骨の間には、歯根膜という組織が存在します。歯根膜が部分的になくなり、その部分の歯と骨が直接接触すると歯と骨が一体化してしまうことがあります。これをアンキローシスと言います。アンキローシスがおこっている場合は、外科的な処置(亜脱臼や部分的皮質骨離断)が必要になります。
装置の種類は?
表側矯正(マルチブラケット装置)

表側の装置。ブラケットと言われる溝つきの装置と、その溝を通るワイヤーで歯を3次元的に動かせる装置。
マウスピース型矯正装置(インビザライン)

プラスチック材料で作られた装置。歯並びをシミュレーションし少しずつ動かしていく装置。
裏側矯正

舌側に装着する装置。舌側に付けられるように改良されたブラケットと、その溝を通るワイヤーで歯を3次元的に動かせる装置。